社長個人の連帯保証は長年の“慣行”ですが、いまは変えられます。
事業承継の現場では、先代の保証を残したまま後継者にも求める「二重徴求」が2割弱、何らかの形で後継者が保証を差し入れる事例は6割弱にのぼり、承継の大きなブレーキになっています。 これに対応して、2014年策定の「経営者保証に関するガイドライン」に2020年4月から事業承継向けの“特則”が設けられ、前経営者と後継者の二重徴求は原則禁止とされました。
さらに一定の条件を満たせば、無保証での新規融資や既存保証の解除が狙え、商工中金の「原則無保証化」や信用保証協会の事業承継特別保証(専門家確認で保証料を最大ゼロへ)といった支援策も整っています。
本記事では以下を経営者視点でやさしく解説します。
- ガイドラインの基本(何を整えれば無保証に近づけるか)
- 承継時に保証リスクを最小化する実務ポイント
経営者保証の基礎とガイドラインの背景・メリット
経営者保証とは何か
中小企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者本人やその家族が会社の借入債務を個人として保証することを指します。これまで多くの中小企業では融資の条件として経営者個人の連帯保証が求められ、万一返済が滞れば経営者や家族の自宅・土地、生命保険などの財産を処分して返済に充てる必要があり、経営者一家の生活が破綻するリスクもありました。
このような重いリスクのため、成長機会があっても借入による思い切った事業拡大を躊躇したり、倒産後の事業再生が困難になるケースも少なくありませんでした。また事業承継の場面でも、将来多額の債務を背負う可能性がある経営者保証の存在が後継者候補にとって大きな心理的負担となり、経営者保証を理由に後継者が事業承継を拒否するケースが多く指摘されてきました。
ガイドライン制定の背景
経営者保証が中小企業の活力を阻害する要因になっていることから、その慣行を見直すために「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と全国銀行協会が事務局となり、2014年2月から運用が開始された自主的なルールです(法的強制力はありませんが、金融機関・中小企業・経営者の自主的な遵守が期待されています)。
このガイドラインでは、法人と経営者の分離、財務基盤の強化、財務情報の正確な把握と積極的な情報開示(経営の透明性確保)という3つの要件を満たす中小企業については、経営者個人に保証を求めない対応を取ることが金融機関に促されています。
ガイドライン適用の具体的な条件は後述しますが、平たく言えば「会社と経営者個人の資産・会計を明確に分け、財務内容を健全かつ透明にすることで、銀行から個人保証なしで融資を受けられる可能性を拓こう」という趣旨です。
ガイドラインの主な内容とメリット
ガイドラインでは上記の要件を満たす企業に対し、金融機関が経営者保証に過度に依存しない融資を検討することを定めています。その結果、中小企業経営者にとって次のようなメリットが期待できます。
- 経営者保証なしで新規融資を受けられる可能性
ガイドラインの条件を満たせば、金融機関から経営者保証なしで融資を受けられる道が開けます。実際、経営者保証に依存しない融資は年々拡大傾向にあり、ガイドラインの運用開始以降その件数は着実に増加しています。 - 既存の経営者保証の解除(外すこと)
条件を満たすことで、現在提供している個人保証について見直し・解除が認められる可能性があります。経営が安定し財務状況が改善すれば、金融機関との交渉によっては「社長保証を外す」ことも不可能ではありません。 - 万一の債務整理時の救済措置
不幸にも事業が行き詰まり債務整理や廃業を行う場合でも、ガイドラインを活用し一定の要件を満たしていれば、金融機関との協議により経営者の自宅(過度に豪華でないもの)や当面の生活費など必要最低限の資産を手元に残すことが認められる可能性があります。
さらに、処分後になお残る債務について原則として免除される(金融機関が請求しない)取り決めも含まれており、経営者個人が自己破産に至らず再起を図れるよう配慮されています。こうした措置により、早期の事業再生や円滑な退出を支援することがガイドラインの目的です。
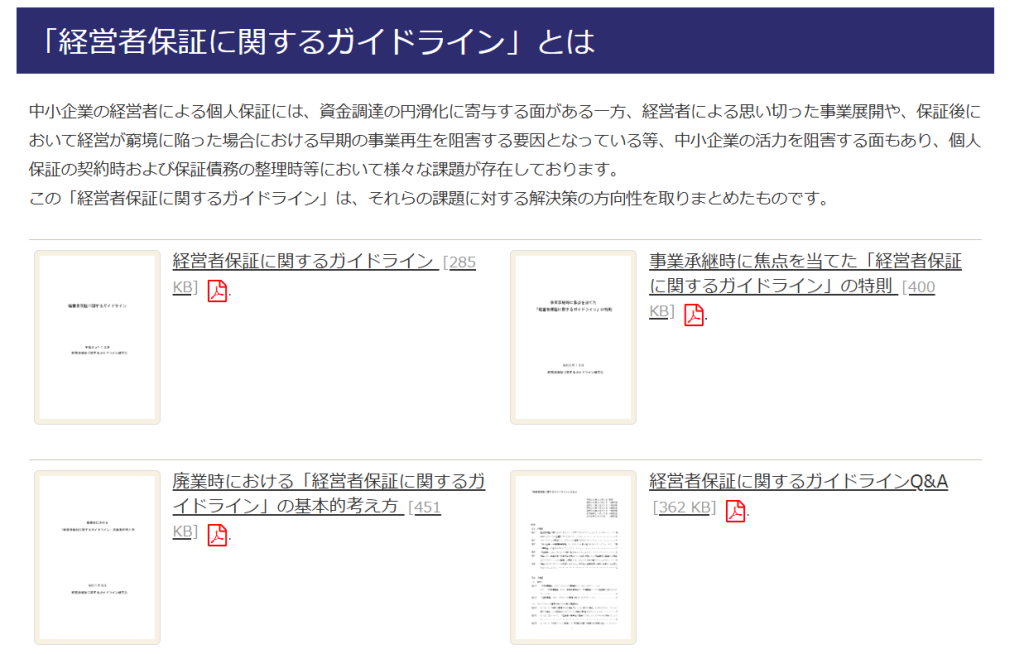
参考元:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
事業承継における経営者保証ガイドライン活用のポイント
後継者問題と経営者保証
中小企業の事業承継では、経営者保証が後継者確保の大きな障害となっています。中小企業庁の調査によれば、後継者候補が事業承継を躊躇・拒否する理由の約6割が「経営者保証の負担」で占められています。
また、事業承継時に先代経営者の保証を残したまま後継者にも個人保証を求めるケース(いわゆる「二重徴求」)は全体の2割弱に上り、二重徴求を含めると後継者が何らかの個人保証を提供しているケースは約6割にも達するという実態があります。こうした状況では、後継者にとって事業を引き継ぐハードルが非常に高くなってしまいます。
ガイドライン「特則」の制定
上記のような問題を解消し、中小企業の円滑な事業承継を促進するため、2019年12月に事業承継に特化した「経営者保証ガイドラインの特則」が策定され、2020年4月から適用が開始されました。
この特則では「前経営者と後継者の双方から二重に個人保証を徴求しない(原則として禁止)」ことが明確に打ち出され、金融機関は原則として先代と新経営者の両方に保証を求めることをしない運用へと転換しています。その結果、上記の二重保証による後継者の負担が大きく軽減される効果が期待されています。
加えて特則では、事業承継時における金融機関と保証契約の見直し・調整について次のようなポイントが定められています。
- 後継者に対する保証契約の柔軟な対応
後継者からの経営者保証徴求が事業承継の妨げとならないよう、金融機関は保証の必要性を改めて検討し、仮に前述のガイドライン要件を完全には満たしていない場合でも総合的な判断で後継者から保証を取らない対応ができないか真摯かつ柔軟に検討することとされています。
要するに、「条件未達でも後継者に保証を求めず融資できないか前向きに考えてほしい」というスタンスです。 - 先代経営者の保証契約の適切な見直し
既に引退した先代(前経営者)が引き続き個人保証を提供している場合、その契約を適切に見直すことも金融機関に求められています。特に事業承継後、前経営者が役員や大株主でもないにもかかわらず保証人のままになっているケースでは、保証の解除・縮減を慎重に検討するよう促されています。
これは、引退後も前経営者が債務リスクを抱え続ける不合理を是正しようという趣旨です。
金融支援策の活用
ガイドライン特則の運用開始と合わせ、事業承継時の経営者保証負担を軽減するための具体的な支援策も整備されました。
例えば政府系金融機関である商工組合中央金庫(商工中金)では、2020年1月よりガイドラインの趣旨を徹底し、一定の条件を満たす企業への新規融資については原則として経営者保証を求めない方針を打ち出しています。実際、年間約3万件の融資でこの「原則無保証化」運用が開始され、従来35%程度だった無保証融資の割合を大幅に引き上げる見込みとされています。
また、各地の信用保証協会では事業承継時に経営者保証を不要とする新たな制度(事業承継特別保証制度)が創設されました。この制度を利用すれば、後継者は個人保証なしで資金調達が可能になるうえ、専門家(経営者保証コーディネーター)による事前確認を受けることで保証協会への保証料率が大幅に軽減され、ほぼゼロ(0.2%程度の事務コストを除き)にまで引き下げられる仕組みです。
さらに、この特別保証制度では既存借入の借り換えによって現在提供中の経営者保証を外すことも可能となっており、中小企業の円滑な事業承継を金融面から後押ししています。必要な要件(事業承継計画の策定・実施や一定の保証限度額等)を満たす企業であれば、ぜひこうした制度の活用を検討すると良いでしょう。
実務的なアドバイス
経営者保証ガイドラインおよび特則を最大限に活用するには、経営者側の計画と働きかけも重要です。まずは金融機関との積極的なコミュニケーションを図りましょう。銀行担当者に自社の状況を説明した上で、「どのような条件を整えれば経営者保証なしの融資が可能になるか」などを率直に相談し、金融機関の意向や基準を把握することが第一歩です。
その上で、自社の財務体質の改善や法人・個人分離の徹底などガイドライン要件を満たすための中長期的な計画(事業承継計画含む)を策定し、着実に実行していくことが大切です。
計画策定にあたっては専門家の力を借りるのも有効でしょう。事業承継計画がしっかりしていれば、信用保証協会の特別保証制度の利用や金融機関からの評価も得やすくなります。最後に、こうした取り組みや計画の進捗については定期的に金融機関へ情報開示・報告し、信頼関係を構築・維持することが肝要です。
金融機関との良好な関係があってこそ、経営者保証解除への道筋が見えてきます。経営者保証ガイドラインというツールと支援策を上手に活用し、将来的に「社長の個人保証なしでも大丈夫な会社」への脱皮をぜひ目指してみてください。








