企業が本業で得た余剰資金を運用する際には、「投資目的」「投資期間」「投資規模」「法人形態」「リスク許容度」の観点から戦略を立てることが重要です。
本業に支障をきたさない範囲で効率的に資産運用を行い、安定収益の確保や資産の成長、さらには税負担の適正化を図ることができます。
以下では各観点ごとに適した投資手段とそのリスク・リターン特性、税務上の扱いについて整理し、最後に条件別の最適ポートフォリオ例を考察してみたいと思います。
投資目的別の投資手段と特徴
企業が余剰資金を運用する目的によって、選ぶべき投資先や戦略は異なります。
主な目的として「安定収益の確保」「キャピタルゲインの追求」「節税対策」の3つに分類し、それぞれ適した投資手段と特徴を解説します。
安定収益の確保(インカムゲイン重視)
安定した利息・配当・賃料収入など定期的な収益の確保を目的とする場合、元本の安全性が高く定常的なインカムゲインを生む資産が適しています。具体的な投資手段と特徴は以下の通りです。
- 銀行預金・国債・社債(高格付け債券)
信用度の高い国や優良企業の債券は、元本割れリスクが極めて低く定期的な利息収入を得られます。定期預金よりやや高い利回りを期待でき、安全性と収益安定性のバランスが良い典型的な運用先です。利息収入は法人税の課税対象ですが、法人の余剰資金運用ではまず債券投資の検討が基本となります。一般に円建て債券の利回りは低水準ですが、為替リスクを許容できれば外貨建て債券で利回り向上を図る方法もあります(※為替差損益に注意)。債券利息は全額が益金(課税所得)となり、受取時に源泉徴収された税金は期末に法人税額と清算します。 - 不動産投資
企業がオフィスビルやアパート等の収益不動産を取得し賃貸運用することで、家賃収入という安定したインカムゲインを得られます。不動産収入は景気に左右されにくく、中長期で本業以外の収益源を確保する手段として中小企業オーナーにも人気があります。さらに減価償却費を計上できるため節税効果や資産保全効果も期待できます。例えば賃貸不動産の減価償却費によって賃料収入の一部を相殺し、課税所得を圧縮することが可能です。ただし不動産は流動性が低く、売却による換金には時間とコストがかかる点に注意が必要です(景気悪化時にすぐ現金化できないリスク)。 - 高配当株式・インフラファンド・REIT等
比較的安定したキャッシュフローを持つ上場株式や上場投資信託(ETF)の中には、配当利回りが高く定期収益源となるものがあります。電力・通信などディフェンシブ株やJ-REIT(不動産投資信託)などは安定配当を狙う投資先として検討できます。ただし元本価格の変動リスクがあるため、単独の株式投資は「安定収益目的」においては比重を上げすぎないよう注意が必要です。株式配当金には法人税が課税されますが、一定要件を満たす株式等の配当は受取配当益金不算入(配当の一部非課税)の適用があります。例えば法人が公募株式投資信託のうち特定株式投資信託(国内株式型など)を保有する場合、受け取る分配金の20%相当額が益金不算入となり、二重課税が軽減されます。
メモ:
安定収益重視の場合でも、インフレ進行時は預金や固定利付債券だけでは実質価値が目減りするリスクがあります。余剰資金に余力があれば、一部を外貨建資産や変動金利商品に充てることでインフレヘッジを図ることも検討されます。
キャピタルゲイン狙い(資産価値の成長重視)
余剰資金を長期的に成長させること(資産価値の増大)を主目的とする場合、価格変動リスクはあるものの高い成長性が見込める資産への投資比率を高めます。キャピタルゲイン狙いの代表は株式などのエクイティ投資で、以下のような手段があります。
- 国内外の株式投資
株式は価格変動が大きいものの、長期的には債券を上回る高いリターンが期待できます。特に新興企業や成長産業への投資は大きなキャピタルゲインの可能性があります。本業が安定している企業や、資産管理会社など長期運用できる法人ではポートフォリオの中核を株式で構成しうるでしょう。例えば世界最大級の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も国内外株式に50%を配分し、債券50%との分散で長期運用し好成績を収めています。短期的には評価損が出る四半期もありますが、長期ではリターンが安定して積み上がっている点は示唆的です。なお法人が株式売買益を得た場合、その益金には通常の法人税率(約23~30%前後)が適用されます(個人の株式譲渡益課税20.315%より高率ですが、法人ならではの損益通算等のメリットがあります)。 - ベンチャー投資・PEファンド等
未上場企業への出資、ベンチャーファンドやプライベートエクイティ(PE)ファンドへの投資は、ハイリスク・ハイリターンの典型です。成功すれば数倍以上のリターンも見込めますが、失敗すれば元本毀損の恐れもあります。資産管理会社など高いリスク許容度を持つ法人のみが検討すべき領域です。これらの投資から得られるキャピタルゲインも法人税課税対象ですが、損失が出た場合は他の益金と相殺して節税効果を得られる点は法人投資のメリットです(※損失の繰越控除も10年間可能)。 - 不動産のバリューアップ投資
不動産も安定収益源になり得ますが、あえて築古物件を安く買ってリノベーション後に高値で売却するなど、売買差益狙いの不動産投資もキャピタルゲイン戦略の一つです。専門知識と市場分析力が求められますが、法人で不動産事業を手掛ける場合はこのような手法で大きな利益を狙うケースもあります。売却益は法人の事業所得となり課税されますが、取得時にかかった費用(修繕費や減価償却費など)は経費計上できるため、純利益に対して課税される仕組みです。
メモ:
法人がキャピタルゲイン狙いで積極運用する場合、年度末の含み益への課税に留意が必要です。法人保有の有価証券が「売買目的有価証券」とみなされると、決算時に未実現の評価益も益金に算入され課税されることがあります。長期保有の方針である場合は、会計上「その他有価証券」として扱うことで評価益を期末計上しない選択も可能ですが、運用目的と会計区分の整合に注意しましょう。
節税目的(税負担の軽減・繰延)
中小企業オーナーなどでは「余剰資金を有利に活用して法人税等の税負担を減らしたい」というニーズもあります。投資自体による利益追求よりも、課税の繰延や圧縮効果を重視する戦略です。ただし税制優遇のための制度(例えば個人向けのNISAなど)は法人には使えず、基本的に法人税計算上は運用益も本業益と合算され課税対象となります。その中で節税効果を狙う主な方法は以下の通りです。
- 損益通算の活用
法人は所得区分が分かれていないため、投資損失と本業利益を自在に相殺可能です。例えば本業が黒字であれば、あえて評価損の出ている有価証券を決算前に売却して損失を確定させ、本業利益と相殺することで法人税を圧縮できます。本業赤字の年は逆に、含み益のある投資資産を売却して利益計上しても相殺されるため課税されずに済みます。損失の繰越控除(最長10年)も可能なので、仮に投資の損失が出たとしても、将来の利益とぶつけて税金を減らす長期節税策も取り得ます。 - 法人保険の活用
法人契約の生命保険に加入し保険料を支払うと、その保険料の一部または全部を損金算入(経費化)できます。例えば、「定期保険特約付き終身保険」など一定の要件を満たす商品では、支払保険料の半分をその期の経費とし課税所得を圧縮可能です(※2019年の税制改正で保険料損金算入ルールは厳格化されました)。保険加入による節税は厳密には税金の永久削減でなく“課税の繰延”である点に注意が必要です。契約期間中は毎期保険料を経費にでき法人税が減少する一方、満期解約時には多額の解約返戻金が益金(収益)となり課税されます(結果としてトータルではプラスマイナスゼロのケースが多い)。繰延効果を高めるには、解約時に役員退職金の支給など別の損金項目を発生させて相殺する手法もあります。 - 減価償却による圧縮
資産への投資も有効な節税策です。例えば余剰資金で社用車や設備、あるいは太陽光発電設備などを購入すれば、その取得費用を減価償却費として数年間にわたり損金計上できます。初年度に即時償却や特別償却の適用がある資産なら、当期利益を大きく圧縮し節税が可能ですu-ks.jp。また収益不動産の購入も、賃料収入源の確保と同時に建物部分の償却費による課税繰延効果があります。将来的に資産売却時には譲渡益が発生し課税され得ますが、それまでの期間に利益圧縮と資金繰りの改善を図れる点で有用です。 - 特定の金融商品による節税
一部の金融商品は法人税法上の特例で税優遇があります。前述の特定株式投資信託の分配金に対する益金不算入(20%非課税)もその一つです。また投資信託の含み損益に関しては、売買目的有価証券でない限り期末課税されないため、含み益を繰り延べやすいという側面もあります。さらに、航空機やコンテナリース事業への匿名組合出資(オペレーティングリース)により、減価償却費相当の損失配分を受けて節税するスキームも富裕層向けに存在します(高度な専門スキームのため要専門家検討)。
メモ:
節税目的の投資は本末転倒に注意が必要です。本来、投資で損失を出して税金を減らしても、損失額以上に資産が減っては意味がありません。「税金を払うくらいなら無駄になっても損金を出したい」という発想は危険で、節税効果と投資リスクのバランスを見極める必要があります。税務上有利でもリターンが著しく低い商品には安易に飛びつかず、まずは本業への再投資や安全資産での運用など基本に立ち返りましょう。

投資期間(運用期間)別の投資戦略
余剰資金をどの程度の期間運用に回せるかによって、適切な投資対象は異なります。一般に短期運用ほど元本流動性と安全性を重視し、長期運用ほど高リスク資産への配分を増やしてもよいとされます。
ここでは短期(1年以内)・中期(おおむね1~5年)・長期(5年以上)の3区分で、それぞれの期間に適した運用について述べます。
短期運用(目安:1年以内)
運転資金の一時的な余剰など近い将来に使う可能性がある資金は、元本確保と流動性確保が最優先です。短期運用に適した手段は以下の通りです。
- 普通預金・短期定期預金
即時換金性が高く安全性も万全です。利回りは僅少ですが、企業によってはメガバンク等が提供する「事業性預金(無利息だが全額預金保護)」と「定期預金(利息付与、一定額まで預金保護)」を用途別に使い分けることもあります。利息には源泉徴収(15.315%)がされますが、法人税申告で税額控除されるため最終的には法人税率で課税されます。 - 短期国債・公共債、譲渡性預金(CD)
満期が数ヶ月~1年程度の国庫短期証券や地方債、銀行のCDなどは、比較的安全かつ預金よりやや利回りが見込める短期運用手段です。市場で売却も可能なため流動性も高いです。安全性の高い債券であれば元本割れリスクは極小ですが、金利変動によっては市場売却時にわずかな価格変動益・損が発生する可能性があります(満期まで保有すれば額面で償還)。短期債の利息や償還差益も益金に算入され法人税課税となります。 - コーポレート型MRF等のマネー・マーケット・ファンド
証券会社の法人口座で運用できるMRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、株式を含まず公社債等で運用される安全性の高い短期ファンドです。毎日決済可能で流動性が高く、コールローン市場金利等に連動したわずかな利回りが付きます。事実上企業の余剰資金の待機場所として活用されます。ただしMRFの分配金にも法人税が課される点は預金利息と同様です(一般に源泉徴収後に受取)。
短期運用では「いざという時にすぐ現金化できること」が肝心です。たとえ利回りが多少低くても、短期の余裕資金は無理にリスク資産へ振り向けない方針が基本となります。
企業財務としても、短期余剰資金は設備投資や債務返済への備えでもあるため、安全資産で保全する意義が大きいと言えます。
中期運用(目安:1~5年程度)
1年以上数年以内の運用期間が見込まれる資金は、短期ほど厳格に流動性を求めなくてもよい代わりに、大きな価格変動リスクは避けたいところです。
中期運用では満期の異なる債券を組み合わせる、安定資産と一部リスク資産を織り交ぜるなどの手法が適します。
- 債券の年限分散投資
例えば1年・3年・5年満期の債券を組み合わせて保有すれば、毎年ある程度の償還金を得つつ全体として中期運用ができます。複数年にまたがる社債・国債を梯子上に配置することで、各年に順次キャッシュ化できるタイミングを増やし、緊急資金需要にも備えることが賢明とされています。債券は満期まで保有すれば元本確保されますが、途中売却では市場金利次第で損失になる可能性があるため、複数債券で年限分散することがリスク低減に有効です。 - 安定型投資信託・バランスファンド
中期であれば、国内外の公社債を中心に一部株式を組み入れたバランス型の投資信託も選択肢です。専門家が運用するファンドに資金を預けることで、自社で個別銘柄を選ぶ手間なく分散投資が実現できます。中期的に年数%台の利回りを狙う運用商品として適しています。ただし法人が投資信託を保有する場合、毎期末の評価に注意が必要です。売買目的で購入した場合は毎期評価替えして含み益が益金になる可能性があります。一方、中長期保有目的であれば期末評価益を計上しなくてもよい運用区分を選択できます(会計処理上の工夫)。 - 高流動性の株式・ETF
投資期間が数年取れるなら、一部は株式や株式指数連動ETFに投資しリターン向上を図ることも考えられます。短期では株価変動リスクが高いですが、3~5年程度保有できればある程度の値下がりも回復が見込める期間と言えます。配当も得られれば中期のインカム確保にもなります。ただし目先数年で確実に使う予定のある資金は株式には投じないのが無難です。株価急落局面が運悪く重なると、中期でも元本回復が間に合わない恐れがあるためです。
長期運用(目安:5年以上)
5年以上使う予定のない資金であれば、インフレや機会損失への対策も兼ねて積極的な運用が検討できます。長期運用ではリスク資産比率を高め、広範な分散投資によってポートフォリオ全体の成長を図ります。
- 株式への厚めの投資配分
長期であれば株式の割合を高めることが合理的とされています。例えばノルウェー政府年金基金は株式60~80%・債券20~40%のポートフォリオで長期運用し、高い累積収益を達成しています。長期なら一時的な暴落による評価減も、時間をかけて回復・上昇する可能性が高まります。自社にすぐ必要としない資金であれば、国内外の株式市場に幅広く投資し、経済成長の果実を取り込む戦略が取れます。ただし株式比率を高めるほど短期の評価変動幅は大きくなる点に留意し、長期目線で評価することが重要です。 - 海外資産・通貨分散投資
長期では自国通貨の信用リスクや低金利による運用難にも備え、外国債券・外貨建て資産への分散も意義があります。特に日本は長らく低金利政策が続き国内資産のリターンが低いため、米国債など利回りの高い海外債券や、成長力のある新興国株式などを組み入れることで、ポートフォリオ全体の期待リターンを高められます。ただし為替変動による目減りリスクも伴うため、為替ヘッジの利用や、自社事業との関係でヘッジになる通貨を選ぶ(輸入業ならドル資産保有など)工夫も考えられます。 - オルタナティブ投資
長期運用では、一部をヘッジファンド、不動産ファンド、インフラ投資、コモディティなど代替資産に充てることもあります。これらは市場伝統資産(株式・債券)との相関が低い場合が多く、ポートフォリオの分散効果を高めます。例えば安定運用型のヘッジファンドは、市場平均を上回るリターンを狙いつつ下落相場でも収益を追求する運用商品で、上下両局面で安定した成績を目指すため長期の資産形成に寄与します。もっとも最低投資額が大きいケースもあり、中小規模の資金では専ら公募投信経由で参加する形になります。
長期運用では「リスク資産の比率を高めつつも分散を効かせる」ことが鍵で。株式偏重に傾きすぎず一定の債券や現金を組み入れることで、暴落時のクッションとしつつ長期複利収益を狙うバランスが求められます。
長期にわたり運用できる資金は企業の将来に向けた準備金とも言え、インフレや経済環境の変化にも耐え得るポートフォリオ構築が大切です。

投資金額規模別の運用先
余剰資金のボリューム(投資に回せる金額規模)によっても、取り得る投資手段やポートフォリオ戦略は変わってきます。
一般的に投資可能額が大きいほど高度な分散投資や専門的な運用手法を実行しやすい反面、金額が小さい場合はシンプルでコスト効率の良い方法を選ぶ必要があります。ここでは数百万円規模・数千万円規模・億単位規模の3つに分け、それぞれに適した運用アプローチを説明します。
数百万円規模の場合(中小企業の小規模余剰資金など)
余剰資金が数百万円(数百万~一千万円未満)程度と比較的小規模な場合、個別の大型投資案件よりも手軽に分散投資できる金融商品が適しています。代表的には以下のような方法があります。
- 投資信託(インデックスファンド等)への投資
少額から幅広い資産への分散投資が可能な手段です。例えば100万円を世界株式インデックスファンドに投じれば、1社株を買うより遥かに多くの企業にまたがる分散効果が得られます。専門知識がなくても市場平均並みのリターンを狙えるメリットがあり、手元資金が少なくてもリスクを抑えつつ資産を増やすことを目指せます。法人がインデックスファンドを保有する際の税制上の特別な優遇はありませんが、運用益が出れば本業利益と合算して課税され、損失が出れば他の所得と相殺できます(法人課税では所得の種類を問わず損益通算が可能)。 - 少額からの株式・ETF投資
資金が数百万円でも、ネット証券を通じて小口の株式やETFをポートフォリオに組み入れることは可能です。例えば「高配当ETF」に100万円、「社債ETF」に100万円という形であれば、安定収益と分散投資を兼ねられます。もっとも少額資金では銘柄数を増やしすぎると売買手数料比率が高まるため、ETF等パッケージ化された商品を活用してコスト低減に努めることが大切です。 - 社内預金・社債枠の活用
あまりに運用額が小さい場合、無理にリスクを取るよりは銀行預金や安全な債券で寝かせておく方がコストに見合うこともあります。社債等は最低購入金額が高めのケースもあるため、まずは預金+αで少額債券という形で、着実に利息収入を得つつ規模拡大を待つ戦略も一案です。
金額が小さい場合、「投資で大儲け」より「遊ばせず有効活用」との発想が重要です。無理に高リターンを狙わず、預金に近い感覚でローリスク資産から始め、徐々に知見を深めて運用額を増やしていくのが堅実でしょう。
数千万円規模の場合(中堅企業の余裕資金など)
数千万円(おおむね1,000万~数億未満)クラスの余剰資金になると、ポートフォリオの多様化余地が広がり、本格的な資産運用戦略が立てられます。
- 国内外の複数資産への分散投資
債券・株式・不動産・現金といった主要資産クラスにまんべんなく配分する分散ポートフォリオ運用が現実的になります。例えば「国内債券20%・外国債券20%・国内株式20%・外国株式20%・不動産10%・現預金10%」のようなバランス型ポートフォリオを構築することで、一部資産の不調を他で補う安定運用が期待できます。中堅規模の製造業などでも、社内留保金の一部をこのような形で運用に回し、インフレや為替変動リスクに備えるケースがあります。 - 収益不動産や設備投資への充当
数千万円あれば、中古マンション1棟やオフィス区画の取得も視野に入ります。本業と関連が薄い不動産投資は慎重な検討が必要ですが、中長期での安定収益と節税効果を見込んで収益不動産を取得する中小企業オーナーも少なくありません。また、遊休資金であっても企業成長に資する設備があるなら、思い切って設備投資に充てるのも一つの運用と言えます(税制上の即時償却や税額控除が得られるケースもあります)。金融投資と事業投資のバランスを検討できるのがこの規模の特徴です。 - 外部専門家や運用商品の活用
資金規模が大きくなると、自社内で運用判断を行う難易度も上がります。信託銀行のラップ口座やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)経由での助言サービスを利用し、プロの手を借りてポートフォリオ運用を行う企業もあります。運用管理コストはかかりますが、自社にノウハウが無い場合は専門家を起用してリスク管理を徹底することが大切です。
この規模の資金運用では、リスク許容度に応じた資産配分戦略が収益を大きく左右します。
例えば保守的な方針であれば国債・国内債券の比率を増やし、積極方針であれば株式や海外資産の比率を増やすなど、基本方針の明確化が重要です。
億単位規模の場合(大企業の剰余金・資産管理会社の運用原資など)
運用余剰金が億円単位(数億~数十億以上)ともなれば、もはや社内「財務部門での資産運用」レベルとなり、機関投資家に近い高度な運用も可能です。
- グローバル分散投資の本格展開
十分な資金量があれば、地域・資産クラス・通貨を跨いだ高度なグローバル分散ポートフォリオを構築できます。例えばGPIFが国内債券・外国債券・国内株式・外国株式を各25%で運用するように、大口資金の場合は全世界の市場にダイナミックに投資することが可能です。加えて一部資金をPEファンド・ヘッジファンド・インフラ事業などオルタナティブ資産に配分し、超長期でリスク分散とリターン追求を図ることもできます。資産管理会社などでは自社をファミリーオフィスのように運営し、富裕層の機関投資家化を目指すケースもあります。 - 社債発行やM&Aとの連携
大企業の場合、自社の資金運用だけでなく資本政策とも連動します。余剰資金で他社の株式取得やM&Aを行えば、単なる運用益以上の戦略的利益を得られるでしょう。また余剰資金が多額な場合、逆に社債を発行せず自己資金で事業投資を賄う選択や、自己株買いで株主還元を行う判断も出てきます。このように運用と経営戦略を統合的に考えるのが大企業の特徴です。 - プロの資産運用チーム編成
数十億円以上を運用するとなれば、社内に専門人材を置いて常時マーケットを監視・分析することも現実的です。運用部門を社内バンカーのように育成したり、著名トレーダーを採用して社内ファンドを作る企業もあります。もっとも多くの事業会社では、本業専念のため運用は信託銀行や運用会社に全面委託するケースが多いでしょう。その際も運用ガイドライン(基本方針)は自社で定め(例:「安全重視:国債比率〇%以上」「ハイリスク資産は〇%まで」等)、委託先をきちんと管理することが重要です。
億単位になると、運用収益も億単位で上下する可能性があります。したがってリスク管理は一層シビアになり、ストレステストや四半期ごとのポートフォリオ評価などガバナンス体制を整える必要があります。同時に、これだけの資金力がある企業は本業投資の機会も豊富でしょうから、常に「運用 vs 本業の資源配分」を見直し、最適な余剰資金額を把握する経営戦略が求められます。
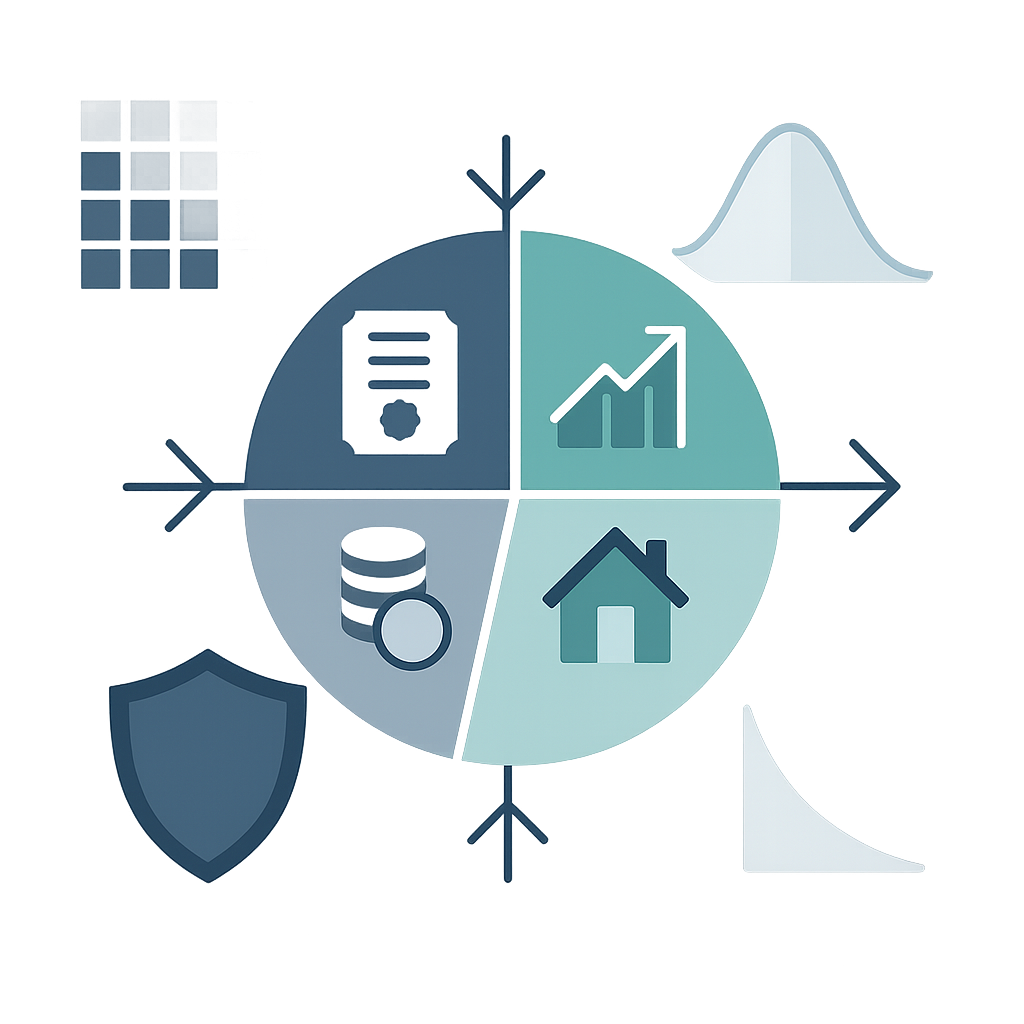
法人形態別の留意点と投資戦略
法人の種類(事業内容や法的性質)によって、資産運用に対する姿勢や制約も異なります。ここでは中小企業(一般事業会社)・医療法人・資産管理会社の3類型に分け、それぞれの特徴と適した運用について解説します。
中小企業(一般事業会社)
中小企業では、本業の業績や資金繰りに直結するためリスク許容度は低めで、資産運用は基本的に「余剰資金で安定運用」が大前提です。以下、中小企業が運用に取り組む際のポイントです。
- 運用割合の節度
中小企業では余剰資金が潤沢でも、それを運用に回しすぎると「本業をおろそかにしているのでは」と金融機関から見做され、融資にマイナスの印象を与えかねません。一般に運用資産が総資産に占める割合は適正水準に留め、本業資金が手薄にならないようにする必要があります。余剰資金運用はあくまで副次的なもので、本業利益の創出が最優先です。 - 安全重視の運用先
中小企業がまず検討すべきは前述の安定収益型の運用、具体的には預金・債券・安全性の高い投資信託などです。社長が100%株主の会社では、運用で損失が出ればダイレクトに会社とオーナー個人の財産が目減りします。したがって**「元本保証に近い商品で、預金よりは有利」**くらいの堅実なスタンスで良いと言えます。実際、債券投資は中小企業の資産運用でもっともポピュラーな選択肢です。 - リスク商品への慎重姿勢
株式など値動きの大きい資産は、運用経験の乏しい中小企業では慎重に扱うべきです。どうしても興味がある場合は、余剰資金の一部(例:20%程度)に留めるか、あるいは投資信託経由で分散を効かせるなどリスク低減策を講じましょう。金融機関から勧められるまま複雑な仕組債などに手を出すのも禁物です。理解できない商品には手を出さないという鉄則を守ることが、中小企業にとっては特に重要です。 - 税務面の検討
中小企業は資本金1億円以下であれば年間800万円まで軽減税率(15%)が適用されるなど税優遇があります。運用益も本業益と合算されるため、利益圧縮策としての運用も中小企業では有効に機能し得ます。例えば本業が黒字で税負担が重い場合、運用でわざと含み損を抱えたまま年度を跨ぎ、将来本業が減益になったタイミングで損失確定して相殺するといった調整も可能です。もっとも節税のためだけの投資はリスクも伴うので、税効果はあくまで副次的な判断材料としましょう。
医療法人
医療法人は医療法によって剰余金の分配が禁止されている非営利性の高い法人形態です。その性質上、「医療以外での投資活動は認められていない」という誤解もありますが、実際には定款の範囲内で余剰資産の運用は可能です。
厚生労働省のモデル定款では、医療法人の資産運用について次のような規定があります。
厚労省モデル定款(特定医療法人)より抜粋
「資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する」
つまり「預金か国公債等の安全な有価証券で運用しなさい」という趣旨であり、医療法人は極めて手堅い運用に徹する必要があります。具体的な運用の特徴は以下です。
- 運用可能な資産の限定
上記モデル定款の解釈では、日本国債および日本国債と同等以上の信用格付けを持つ有価証券が運用対象となります。日本国債の格付け(S&P社でA+)以上であれば、安全性が高いとみなせるため、例えば米国債(AA格)や高格付けの普通社債も選択肢に入ります。ただし為替リスク等については各医療法人の理事会や所轄庁の解釈次第で異なる扱いとなる可能性があるため、基本的には国内の国債・地方債・銀行預金など円建てで確実性の高い資産に限定する法人が多いようです。 - 元本保全と利回りの両立
超低金利下では日本国債や預金の利息は極めて低く、医療法人の資産も目減りしかねません。そこで一部の医療法人では、モデル定款の趣旨に反しない範囲で比較的利回りの高い資産(例:米ドル建て債券)に投資する動きもあります。米国債は日本国債より格付けが高く利回りも高いため、「日本国債以上に確実な有価証券」として理論上は運用可能との見方です。もちろん為替変動リスクは伴いますが、利息収入で為替差損をカバーできる「金利のクッション効果」も期待できるとの指摘があります。 - 税制面
医療法人も一般の株式会社同様に法人税が課されます(医療法人は収益事業から生じた所得に課税。医業収入は非収益事業だが附帯事業は課税対象)。運用益は通常「収益事業」として課税されますので、預金利息・債券利息等には課税が及びます。医療法人だからといって運用益が非課税になるわけではない点に注意が必要です(※配当益金不算入など一般法人と同様の税制は適用可能)。
まとめると、医療法人の運用戦略は「安全第一、堅実運用」に尽きます。
許される範囲の中でなるべく有利な金利を追求しつつ、本業たる医療提供に支障をきたさないよう流動性を確保することが肝要です。
資産管理会社
資産管理会社とは、事業活動より資産運用・保有を目的として設立された法人(しばしばオーナー個人が設立するペーパーカンパニーや、不動産管理会社など)を指します。
資産管理会社の場合、まさに運用そのものが事業と言えるため、他の法人形態以上に積極的かつ多様な投資戦略を取り得ます。
- 税制メリットの活用
資産管理会社を個人資産の受け皿として使う主目的は節税にあります。個人で株式や不動産を所有すると配当課税20.315%・不動産所得は累進課税(最大55%超)となりますが、法人で運用すれば原則一律の法人税率(中小法人で実効税率約25~30%、大法人で約30%台)で済みます。さらに所得の種類に関係なく損益通算でき、損失の繰越期間も個人3年に対し法人は10年と有利です。経費計上範囲も広がり、個人では控除できない費用も法人なら損金算入できるケースが多々あります。資産管理会社はこれらメリットを駆使して、所得税・相続税負担の軽減を図りつつ長期運用するのが特徴です。 - 多様な運用資産の組入れ
資産管理会社は基本的に法令範囲内で何に投資しても自由です。オーナー個人の方針次第では不動産、株式、投資信託、金地金、果ては美術品や仮想通貨まで、様々なアセットを組み合わせて運用できます。一般に多いのは、不動産管理会社としてオーナー一族の不動産を集約し賃料収入を上げるケースや、証券投資専門会社として株式・債券ポートフォリオを運用するケースです。いずれにせよ長期的に資産を成長・維持させ、将来オーナーやその相続人に利益をもたらすことが目的となります。 - リスク許容度と運用方針
資産管理会社のリスク許容度は、オーナー個人の財務状況や意向によります。一般に本業収入と切り離された資産管理会社は、多少リスクが高い運用にも踏み切りやすいとされています。例えば余剰資金を全て株式投資に充てていても、本業会社の経営には影響しないため、オーナーの純資産内で調整すればよいだけです。もっともオーナー個人にとっては大事な資産ですから、全額ハイリスク投機というよりは長期的な財産保全と成長をバランスする運用が主流です。株式や投資信託でコア資産を形成しつつ、不動産で安定収益も確保し、さらに保険加入で万一の保障と退職金積立準備をする、といった総合的な財産管理の色彩が強いです。 - 例:不動産管理会社
オーナー経営者が個人で持っていた賃貸物件を資産管理会社に移すことで、家賃収入が法人課税になり個人高税率を回避できます。また相続時も不動産を法人所有にしておけば、評価額圧縮(持分の評価減)や株式譲渡によるスムーズな承継が可能です。運用面では、法人名義で追加物件を購入し規模拡大を図ることもでき、減価償却による節税を繰り返しながらオーナー資産を拡大していけます。注意点は、法人からオーナーへの資金移動には配当課税(二重課税)が伴うため、運用益は極力法人内に留保・再投資して複利運用するのが基本となることです。 - 例:投資顧問会社(自己運用型)
オーナーが金融に明るい場合、自ら代表を務める投資会社を作り、そこで株式・債券・デリバティブ取引を行うこともあります。法人にすればFX等のレバレッジ取引でも経費を落とせ、損益を全体で通算できるため、個人より有利に活発な投機ができます。ただし損失が出ても本業収入でカバーできるわけではないので、オーナーの純資産が毀損するリスクには変わりありません。資産管理会社といえど、破産すればオーナーの財産へ跳ね返ります。したがってリスク管理は怠らず、専門家の助言や複数会社間のリスク分散(不動産会社と証券投資会社を分ける等)も検討されます。
資産管理会社は「法人」とはいえ実質的にオーナー個人の財布なので、運用目標もオーナーの人生計画と一体です。短期的な法人税節約に固執せず、長期的な相続対策・資産形成に資する運用を心がけることが大切でしょう。
リスク許容度別の投資戦略
最後に、企業(経営者)のリスク許容度に応じた運用先の選び方をまとめます。
リスク許容度とは「どの程度の元本変動(損失可能性)を許容できるか」であり、低リスク志向から高リスク追求型まで様々です。以下、低リスク・中リスク・高リスクの3段階で考察します。
低リスク志向の場合
「元本割れは絶対に避けたい」「わずかな利回りでも確実にプラスで終わりたい」という安全重視の姿勢では、投資対象はごく限られます。基本は預金・国債・高格付け債券など前述した安定収益確保型の資産です。
- 期待リターン
年率でせいぜい0%台後半~1%台程度とローリターンになります。超低金利下では企業向け預金金利も0.1%未満であるため、実質インフレ率次第では「リスクなしでも実質目減り」という事態もあり得ます。そのため安全重視でも、少しでも利回りを高める工夫(例:ネット定期預金や社債の活用)が望まれます。 - リスク管理
元本毀損リスクが極小の資産のみで運用するため、価格変動による損失リスクはほぼありません。ただし信用リスクとインフレリスクはゼロではありません。万一発行体の国や企業が破綻すれば債券でも元本割れしますし、預金も上限を超える部分は預金保険で保護されません。低リスク運用の場合、各資産に分散して信用リスクの低減を図る(例:預金先銀行を複数に分散、国債と複数社債を組み合わせ)ことが勧められます。 - 税務上の留意点
安全資産運用では売却益などは基本出ず、利息収入や償還差益が中心となります。これらは全て法人の課税所得となり、他所得と相殺しにくいのが実情です(損が出にくいので通算する必要がない)。したがって低リスク運用では税金面で特筆すべきメリットは少ないですが、強いて言えば「運用による損失リスクがない=本業利益が無駄に相殺されない」という安定経営の利点があります。
低リスク運用は「儲けは小さいが損もしない」のがメリットです。中小企業の余剰資金運用はこれで十分というケースも多く、まずは安全運用で企業として安心感を得るのも一つの戦略です。
中リスク志向の場合
「ある程度の元本変動は許容するが、大損は困る」というバランス志向の場合、株式と債券を組み合わせた分散投資が軸になります。中リスクの典型的ポートフォリオは、例えば株式30~50%、債券30~50%、残りを不動産や現金といった構成です。
- 期待リターン
年率3~5%前後を狙えるイメージです。株式部分が好調ならそれ以上も期待できますが、債券や現金部分があることで全体のボラティリティ(変動幅)は低めに抑えられます。インフレ率+α程度の実質成長を目指すイメージで、長期に複利運用すれば着実に資産拡大が見込めます。 - リスク管理
ポートフォリオ内で資産同士がリスク分散効果を発揮するため、一部が下落しても他が上昇することで損失が緩和される可能性があります。例えば株価急落時には債券価格が上がりやすいといった逆相関も期待できます。注意点は、リーマンショック級の危機では分散効果も限定的でポートフォリオ全体がマイナスになることもある点です。しかしそのような局面でも中リスクポートフォリオなら下落率を単独株式より抑えられるので、回復まで企業体力を保ちやすくなります。 - 税務上の留意点
中リスク運用では株式配当・売却益、不動産賃料、利息収入など様々な収益が生じます。法人税制ではそれら全てが合算され課税されますが、損益通算と損失繰越ができるため、ある投資の損と別の投資の益を相殺可能です。これは分散投資との相性が良く、年度内でプラスの資産とマイナスの資産を抱えていても、トータルプラス分だけに課税すればよい仕組みです。さらに分配金の益金不算入や減価償却による圧縮といった各種税メリットも組み合わせやすいです。総じて、中リスク分散投資は税負担とリスクのバランスが取れた運用と言えるでしょう。
高リスク志向の場合
「元本が半分になる覚悟でも、大きく増やしたい」というアグレッシブな志向では、株式偏重またはレバレッジ運用といった大胆な手法になります。
- 株式・リスク資産集中
資産の大部分(70~100%近く)を株式やリスクの高い商品で占める戦略です。期待リターンは年10%以上も狙える一方で、市場暴落時には評価額が▲30~50%になる可能性もあります。資産管理会社などでは、若いうちに思い切ってリスクを取って増やし、後年安定運用に切り替えるといったライフサイクル投資もあり得ます。四半期や年度で見ると大きな変動がありますが、長期的成功に賭けるスタンスです。 - 信用取引・デリバティブ活用
会社の余剰資金を担保に、信用取引(証拠金を積んで株式購入)や先物取引、FX取引などでレバレッジ(テコ)を利かせれば、自己資金以上のリスクテイクが可能です。例えば1億円を元手に先物で実質5億円分のポジションを取れば、利益も損失も5倍になります。上手くいけば資産急増も見込めますが、失敗すれば元手以上の損失が出る危険もあります。極めて専門的な知識と覚悟が必要なため、一般事業会社には基本的に推奨されません。やるとしても資産管理会社で専門トレーダーを置くなど、リスク管理体制を整えた上で行うべきでしょう。 - 集中投資
特定の株式や商品に資金を集中させるのも高リスク高リターン戦略です。他に分散していない分、当該投資が当たれば大成功、外れれば大失敗となります。企業規模が大きく資金に余裕がある場合、全体の一部資金でこうした集中投資を敢行するケースもゼロではありません。たとえば一部上場企業がベンチャー企業に数十億円出資するようなケースです。本業収益が盤石であればベンチャー投資が失敗しても会社は傾きませんが、成功すれば将来の新事業の柱になる可能性もあります。このように集中と分散を使い分ける戦略も大企業的な発想としてはあり得ます。
高リスク運用は、一歩間違えば会社存続を脅かすため、よほど資金的体力があるか、運用が主目的の法人に限られるでしょう。
税務上は、利益が出れば法人税負担も大きくなります(個人なら20%課税のところ法人だと30%程度)ものの、仮に損失が出ても損金算入できる点は救いです。大勝ちすれば内部留保が積み上がり会社の信用力向上にもつながりますが、大負けすれば内部留保を食い潰すことになります。ハイリスク投資は慎重にというのが鉄則です。
条件別:最適ポートフォリオ例
以上の観点を踏まえ、典型的な条件ごとに有望な投資先とポートフォリオ例を整理します。
下表では、「投資目的・期間・リスク許容度・投資規模・法人形態」の組み合わせ例をシナリオ形式で示し、それぞれに適したモデルポートフォリオとそのリスク・リターン特性、税務上のポイントをまとめています。
| 想定シナリオ (目的・期間・リスク許容度・規模・法人形態) | 投資ポートフォリオ例 | 期待リスク・リターン特性 | 法人税等の扱い(課税・優遇) |
|---|---|---|---|
| 短期・安定収益目的・低リスク運用 例:余剰資金が少額の中小企業(運転資金の一時運用) | ・現預金・MRF等:50% ・短期国公債・高格付社債:30% ・安全性重視の公社債投信:20% | 流動性重視でほぼ元本確保。利回りは年0.1~1%程度と低いが、信用リスクや価格変動リスクは極小。必要時に即現金化可能で、本業への影響を最小化。 | 利息収入が中心で全額益金算入(源泉15.315%控除後、法人税精算)。運用益が小さいため法人税負担への影響も僅少。本業赤字なら利息益と通算可能。特段の税優遇はなし。 |
| 中期・安定収益目的・中リスク運用 例:余剰資金数千万円規模の中小企業(将来の設備投資準備金の運用) | ・国内債券(国債・社債):30% ・外貨建て債券:20% ・不動産ファンド・REIT:20% ・バランス型投資信託:20% ・定期預金(流動性枠):10% | 債券・不動産収益を軸に適度な利回りを狙う中庸ポートフォリオ。期待利回り2~4%程度で、為替や不動産市況による変動はあるが元本変動も比較的限定的。例えば不動産収入は長期固定賃料が多く安定性高い。景気変動で評価損が出る可能性はあるものの、分散効果でリスク低減。 | 利息・配当・賃料・投信分配金など複数収益あり全て課税対象。ただし20%受取配当益金不算入(適用対象の投信分配金等)で一部非課税メリットあり。不動産収入は減価償却で実効税率低下(課税繰延効果)。複数資産の損益通算で課税所得の平準化が可能。 |
| 長期・キャピタルゲイン目的・高リスク運用 例:資産管理会社が長期運用するケース(オーナー資産の積極運用) | ・国内外株式:60% ・成長分野へのPE投資:15% ・外国債券(米国債など):15% ・不動産(国内外):10% | 株式中心の攻めのポートフォリオ。期待リターンは年5~10%以上と高いが、値動きも大きい。仮に全体の8割超をリスク資産に投じれば、四半期・単年度ではマイナスもあり得る。しかし長期では経済成長を取り込み資産倍増も狙える。最悪シナリオではリーマン級で評価額半減リスクも覚悟が必要。 | 売却益・評価益は通常の法人税率で課税(中小法人実効税率25%、大法人30%超)。個人より税率高いが、法人内に利益留保し再投資可能。損失発生時は本業含む他益金と相殺、10年内の将来利益と繰越相殺も可能で損失の税務上救済は手厚い。株式配当益は持株割合等に応じ50%または100%益金不算入も適用可能(グループ会社株など)。全体として、利益が出れば高率課税だが損失時の税効果も大きく、ハイリスクハイリターンの税負担は中程度に緩和される。 |
| 中期・節税目的運用・低~中リスク 例:黒字中小企業が利益圧縮を狙うケース(3~5年スパンの節税策) | ・解約返戻金の高い法人保険への加入(保険料支出) ・減価償却資産への投資(設備、太陽光発電等) ・損出し用の安全資産購入 | リターンより課税繰延効果を優先したポートフォリオ。法人保険は保障を得ながら課税を後年度へ繰り延べる手段で、運用利回りは極めて低い(解約返戻金でトントン~若干マイナス)が、一時的に損金計上できるメリットがある。設備投資は減価償却により初期年度の利益圧縮効果が大きい(太陽光発電等は固定買取収入で元本回収も見込める)。全体として低リスク資産中心だが、節税スキームの失敗リスク(税制改正等で効果減)には注意。 | 法人保険料は一部または全額損金算入でき、当期の課税所得を圧縮。しかし解約返戻金受取時に益金計上が必要で、節税効果は単なる税金の繰延。減価償却資産投資も同様に、取得時に損金計上し減税、その後売却時に益金発生(償却済なら売却益大)となりやはり繰延効果。繰延期間中に退職金支給やさらなる節税投資で出口戦略を図ることで永久繰延に近づける工夫も可能。安全資産の含み損出しも、本業利益との相殺で法人税減少に寄与。総じて、税負担を平準化・先送りすることで実効税率を下げる効果を狙った運用。 |
上述のシナリオは一例ですが、組み合わせによって戦略は多岐にわたります。
自社の目的・状況に合った基本方針をまず定め(例:「当社は余剰資金の○%を○○目的で運用し、△△なリスクは取らない」)、その方針に沿って具体的な資産配分や商品選定を行うことが大切です。
特に中小企業の場合、資産運用は本業あってこその副次的活動であり、運用に熱中しすぎて本業をおろそかにしない節度が求められます。
必要に応じて金融機関や専門アドバイザーの力も借りながら、自社に最適な運用戦略を策定しましょう。

