中小企業が業務の効率化や生産性向上を図るための設備投資を支援する「中小企業省力化投資補助金(一般型)」について、第1回公募(2025年)の採択結果が公表されました。
本記事では、その採択件数や採択率(「中小企業省力化投資補助金 採択率」)のデータ分析結果を紹介するとともに、実際の採択事例から見えてきた省力化投資のトレンドや、今後申請を検討する際のポイントについて詳しく解説します。
補助金の審査傾向を踏まえた申請書作成の留意点や採択されやすい設備投資のキーワード、さらにスケジュール管理のコツや不採択とならないための注意点まで網羅し、最後に本補助金を活用して中小企業が実現できるビジネス変革の可能性についても考察します。ぜひ今後の戦略策定にお役立てください。
第1回公募の採択件数・採択率の概要
令和7年(2025年)1~3月に実施された第1回公募では、申請件数1,809件に対し採択件数1,240件、採択率は約68.5%という結果でした。
これは他の主要な高額補助金の採択率と比較しても非常に高い水準です。
例えば、同時期のものづくり補助金(18次公募)の採択率は約35.8%、事業再構築補助金(第12回)の採択率は約26.5%に留まっており、本補助金の68.5%という数値は際立っています。補助金公募の初回は採択率が高めに出やすい傾向がありますが、それにしても約7割が採択されるという“易き門”となった背景には、公募期間が短く準備不足で申請を断念した企業が多かったことや、支援機関(認定支援機関や専門コンサル等)の積極的な関与で質の高い申請が行われたことなどが影響したと考えられます。
いずれにせよ、第1回公募は想定以上の高採択率となりました。
都道府県別の採択動向
第1回公募では全国47都道府県すべてから採択者が出ました。なかでも採択件数が多かった上位3都道府県は、大阪府(124件)、愛知県(108件)、東京都(93件)で、首都圏の東京よりも製造業集積地である大阪・愛知の採択数が上回る結果となっています。
これら上位3府県だけで全採択案件の約26%を占めており、地域別では産業基盤の強いエリアに採択が集中したことがわかります。
逆に、中国・四国地方など一部地域では採択件数の相対的な少なさも目立ち、地域によって設備投資への取組度合いに差があることもうかがえます。とはいえ地方からも幅広く採択されており、北海道から沖縄まで各地の中小企業が本補助金を活用して省力化投資に踏み出している状況です。
業種別の採択傾向
業種別の採択件数を分析すると、製造業が全体の61.7%と突出して多くを占めました。次いで建設業が11.3%を占め、これら2業種で約7割強を占有しています。
製造業はもともと設備投資意欲が高く人手不足の深刻な業種であり、「専用機による省力化」という補助金の趣旨に最も適合した案件が多かったと考えられます。実際、製造業向けの補助金と言えるほど製造業の採択が目立ち、製造現場での人手不足解消・生産性向上ニーズの強さが伺えます。
一方、建設業も11%超と高く、建設現場の省人化ニーズ(例えば測量や施工管理の自動化など)が追い風になったようです。
これら以外の業種は一業種あたり数%以下の割合に留まりますが、サービス業、卸売業、小売業、運輸業、農林水産業など幅広い業種から採択されています。飲食業や宿泊業といったサービス業向け案件も一定数あり、製造・建設以外の分野でも現場のDX・自動化による省力化への挑戦が評価されたことがわかります。
つまり「製造業偏重」とはいえ、あらゆる業界で省力化への取り組みが採択されうる状況と言えるでしょう。
企業規模別(従業員数・資本金別)の採択傾向
採択企業の規模を従業員数および資本金から見てみると、興味深い傾向が見られます。
従業員数規模
従業員数規模では、「21〜30名」の企業が採択企業中最も多い層でした。5人以下の小規模事業者も全体の12.5%程度存在し、6〜10人規模も13%超と一定数採択されていますが、全体としては従業員数20~30名前後の中小企業が中心となっています。
また100名を超える中堅企業も約12%含まれるなど幅広い規模の企業が採択されていますが、採択企業の多くは「小さすぎず大きすぎない」中堅規模の中小企業といえます。この規模の企業は課題が明確である一方、投資に耐えうる経営体力も備えており、補助金による効果が分かりやすいため審査でも評価されやすいと考えられます。
資本金規模
資本金規模では、「1,000万~2,000万円未満」すなわち1億未満の中小企業が全採択企業の34%を占め最大のボリュームゾーンでした。次いで「2,000万~3,000万円未満」や「500万~1,000万円未満」といった層がそれぞれ1割強を占めています(※個人事業主は資本金0円として別枠集計)。
資本金1億円以上の企業はごく一部(2.4%)に留まり、大半の採択企業は数千万円規模の中小企業です。これは前述の従業員数の傾向と合致しており、一定の経営基盤を持ちながら人手不足などの課題を抱える企業が中心に申請・採択されていることが読み取れます。
言い換えれば、規模が小さすぎると投資余力が乏しく、逆に大きすぎると補助対象から外れるケースもあるため、中核的な中小企業にとって特に活用しやすい補助金と言えるでしょう。
採択事例から読み解く省力化投資の方向性
第1回公募で実際に採択された事業計画名や内容から、各業界における省力化投資の具体的な方向性が見えてきます。以下では製造業・建設業・サービス業(飲食業等)の代表的な採択事例を紹介し、それぞれの業界でどのような省力化ニーズに対応した投資が評価されたのかを探ります。
①製造業の採択事例:ロボット導入と生産ライン自動化
製造業では生産ラインの自動化やロボット導入による省力化が目立ちました。実際に採択された事例を見ると、例えば以下のようなテーマが多くみられます。
- 産業用ロボットアームやAGV(自動搬送ロボット)、自動検査装置の導入 – 人手に頼っていた組立・加工・搬送工程を機械化し、作業負担と人件費を削減。
- AIカメラ(画像認識技術)による外観検査工程の自動化 – 製品の検品工程をAIで無人化し、熟練者不足の課題を解消。
- 熱処理炉の自動搬送システム導入 – 高温危険作業を自動化し、安全性向上と同時に人員削減・高速化を実現。
いずれも製造現場の重労働部分を機械化して人手を省く取り組みです。
採択事例には「溶接ロボット導入による省力化」や「包装工程の自動化ライン構築」といったタイトルが並び、ロボット技術やAIを活用して生産効率を上げる方向性が鮮明です。これらの投資により、24時間稼働や品質の均一化も可能となり、人手不足の克服と生産力向上を両立している点が評価されたと言えるでしょう。
②建設業の採択事例:ICT施工と遠隔・自動化技術
建設業界では、ICTやセンサー技術を活用した施工プロセスの省力化が採択されています。具体的な事例として、以下のような投資テーマが見られました。
- ドローンによる測量の自動化 – 土木工事現場でドローンを飛ばし、地形測量や進捗管理を省力化。人力測量に比べ短時間で広範囲をカバーし、作業負担を軽減。
- 自動追尾式のレベル計測器とBIMソフトの連携 – 建築現場で自動測量機器を導入し、測量データを即座にBIM(Building Information Modeling)に反映。熟練技術者の補助無しでも正確な測量が可能となり、省人化に成功。
- ICT建機(ICT施工機械)の導入 – GPSやセンサー制御された重機を導入し、オペレーターの作業を自動化・補助することで作業効率アップ。
建設業では慢性的な人手不足と高齢化が課題となっていますが、採択案件では測量や設計、施工管理といった工程のデジタル化によって、限られた人員でも業務が回る仕組みづくりが評価されています。
例えば「新型測量機器の導入・連携運用で測量作業の省力化」や「ICT建機導入による土木工事の改善」といった案件が採択されており、現場作業のICT化・遠隔化がキーワードです。これにより作業精度向上や安全性向上も同時に達成できるため、単なる人減らしでなく生産性革命として評価されたと言えるでしょう。
③サービス業(飲食・宿泊等)の採択事例:無人化と業務効率化
飲食業や宿泊業などサービス業界でも、省力化投資による業務効率化の事例が見られます。人手に頼りがちな接客・調理・清掃といった現場にデジタル技術を導入して省人化したケースが採択されています。
主な例を挙げると、
- 自動調理機器や券売機、タブレットオーダーシステムの導入 – 飲食店の厨房で炒め物などを自動調理するロボットや、お客様自身に注文入力いただくタブレット端末、セルフサービスの券売機等により、調理や注文受付の人手を削減。24時間営業や人件費抑制にも貢献。
- 清掃管理システムや無人チェックイン設備の導入 – ホテルや旅館で館内清掃の進捗を管理するIoTセンサーシステムや、フロント無人チェックイン機を導入し、フロントスタッフや清掃スタッフの業務負荷を軽減。特にコロナ禍以降、非対面サービスとしての付加価値も評価。
- 業務管理ソフトによるバックオフィス効率化 – 理美容やスクール業などで予約・顧客管理やスタッフシフト管理をアプリ・クラウド化し、煩雑な事務作業を省力化。現場サービス提供に人員を振り向ける余力を創出。
サービス業は製造業に比べて人間らしいサービスが求められる場面も多いですが、それでも自動化できるところは積極的にテコ入れする動きが出ています。
特に飲食・宿泊では深刻な人手不足に対応するため、無人化やセルフサービス化の流れが今後も加速しそうです。採択事例からも「券売機導入でスタッフ業務負担を軽減」といった取り組みが確認できます。
サービス品質を維持・向上しつつ裏方作業を自動化することで、お客様対応など人ならではの業務に人材をシフトさせる狙いが読み取れます。
サービス業の効率化!
申請書作成・事業計画立案時の留意点(審査観点)
高い採択率とはいえ、しっかりとツボを押さえた計画を立てなければ採択は勝ち取れません。申請書や事業計画書を作成する際の留意点として、審査員の視点や最近のトレンドを踏まえ以下のポイントに注意しましょう。
設備ありきの計画にしない
「○○という機械を買いたい」が主目的になってしまう申請は敬遠されます。あくまで解決したい業務上の課題が主役であり、その手段として設備導入が必要であることを明確にしましょう。
「機械を入れれば便利になりそう」といった安直な動機ではなく、現状のボトルネックをどう省力化で解消するかに焦点を当てて記述します。
自社の業務フローに即した具体策
汎用的な表現だけで終わらせず、自社業務のどの工程をどう改善するのかを描きましょう。
例えば「DXで効率化します」だけでは不十分です。現在は○○作業に△△時間/人かかっているが、▲▲システム導入で□□%削減できる、といった具体的なフロー改善と数値効果を示すと説得力が増します。
定量的な効果と根拠
導入後に見込まれる省力化の効果(削減される工数や人員、コスト削減額、生産性向上率など)を数値で示しましょう。さらにその数値の算出根拠や試算プロセスも簡潔に触れると信頼性が上がります。
「○○が△△台導入されれば月◇時間の作業が不要になるため、その分を新規受注対応に充てられる」等、成果を見据えた記述が望ましいです。
賃上げ等の取組も具体的に
本補助金では他の補助金同様、生産性向上による賃上げ等の波及効果も期待されています。申請書内で「○%の賃上げを実施」といったコミットを書く場合は、その財源や根拠を明示しましょう。
単に数値目標を書くのではなく、「省力化で年△円のコスト削減→その一部を従業員給与に充当」等、具体的なメカニズムを示すと評価が高まります。
リスクやフォローアップも考慮
導入した設備が本当に効果を発揮するか、不確実性も伴います。そこで、導入後の効果検証計画や、万一期待通りに進まなかった場合のフォロー策にも触れておくと良いでしょう。
例えば「6か月後に生産量指標をモニタリングし、問題があれば○○を追加導入する計画」といった具合に、計画の実効性を高める工夫を示せれば、審査員にも「きちんと考えている企業だ」という印象を与えられます。
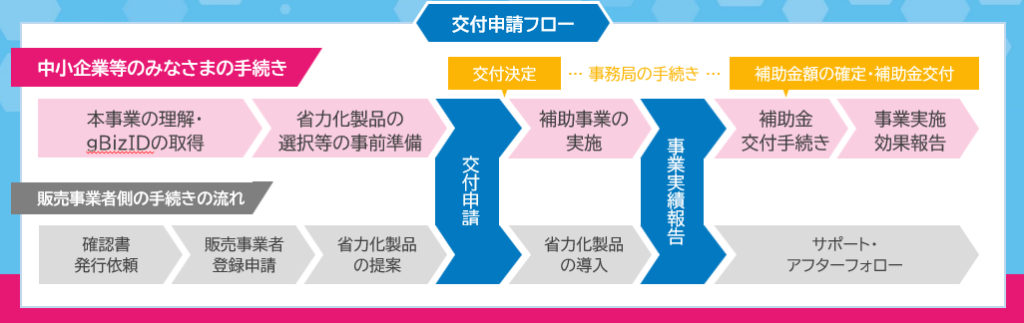
以上のように、審査観点を意識して申請書を作り込むことで、単なる設備購入申請ではなく事業の質を高める投資計画として評価してもらえる可能性が高まります。自社の課題と解決策を丁寧に紐づけ、数字とストーリーで語ることを心がけましょう。
採択されやすい設備投資のパターン・キーワード
第1回公募の採択案件からは、採択されやすい投資テーマの傾向も浮かび上がります。キーワードとして目立ったものをいくつか挙げると次のとおりです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)
業務プロセス全体のデジタル化・システム統合により効率化を図る取組。例えば紙の指示書や職人の勘に頼っていた工程をデータ連携・可視化することで、生産性向上と属人化解消を実現するプロジェクトが散見されました。多くの採択案件に「DX」「デジタル化」といった言葉が含まれており、デジタル技術の活用が肝と言えます。
AI活用
人工知能(AI)や機械学習の技術を組み込み、従来は人間が行っていた判断・検知作業を自動化するテーマです。特に画像認識AIによる検査や需要予測、チャットボットによる問い合わせ対応など、AIで人手作業を代替/補完するプロジェクトが注目されています。
AI活用と書くだけでなく具体的な用途(「AIカメラで不良品を自動検知」等)まで踏み込むと説得力が増します。
ロボット・自動化設備
上述の製造業事例にあるような産業用ロボット、AGV/AMR(自動搬送ロボット)、ドローン、自動加工機などの導入はまさに省力化投資の王道です。
単体の機器導入に留まらず、複数の汎用設備を組み合わせてライン全体を自動化するような高度な取組も見られました。「ロボット導入」「自動〇〇装置」といったキーワードは採択事例で多数確認できます。
IoT・センサー連携
現場のモノや人の動きをセンサーで計測し、リアルタイムでデータ収集・分析するIoTソリューションも重要なトレンドです。
工場内の機械稼働をセンサー監視して予防保全を効率化したり、物流倉庫で在庫を自動カウントするIoT棚卸システムを導入した事例もありました。IoTとソフトウェアを組み合わせたスマート化は、省力化のみならず高度な経営判断にも資する点で評価されるでしょう。
業務効率化・省人化
申請書上で頻出するキーワードとして「業務効率化」「省人化」「無人化」があります。
例えば「無人受付システム導入で受付業務を効率化」や「省人化機械の導入によるライン効率向上」といったタイトルが実際に採択されています。
これらは本補助金の目的そのものとも言える言葉であり、タイトルや計画書の中で適切に使うことで審査員にも意図が伝わりやすくなるでしょう。ただし安易に乱用せず、自社の計画に即した文脈で用いることが大切です。
人材再配置・高付加価値化
単に人件費を削減するのではなく、浮いた人手をより付加価値の高い業務へ振り向ける(人材再配置)という観点も重要です。
実際の採択案件でも「省力化で捻出したリソースを新商品の開発や販路拡大に充当」といった記述が多く見られました。省力化によって社員のスキルアップや新事業への挑戦が可能になることをアピールできれば、「攻めの投資」として高く評価される傾向があります。

以上のようなキーワード・テーマは、第1回採択結果から浮かび上がった「勝ち筋」のパターンと言えます。
ただし大切なのは、自社の状況に合わせてこれらの技術や手法をどう効果的に組み合わせるかです。他社で流行っているからと闇雲にAIやロボットを導入するのではなく、自社の課題解決に本当に有効な手段かを見極め、適切なキーワードを計画に盛り込むようにしましょう。
採択されるための準備とスケジュール管理のコツ
補助金申請は準備が肝心です。
特に本補助金の第1回公募では、公募開始から締切まで約2ヶ月、申請様式公表から締切までは約1ヶ月という非常にタイトなスケジュールでした。第2回以降も同程度の期間で公募が行われる可能性があり、公募開始後に慌てて準備しては間に合わないおそれがあります。
そこで、採択を勝ち取るために有効な事前準備やスケジュール管理のコツを整理します。
- 自社課題の棚卸し: 申請前にまず、自社の業務プロセスを洗い出しボトルネックを明確化しましょう。現場の声を聞き、どの作業に負担や無駄が多いか、どの工程がネックで売上機会を逃しているか等をリストアップします。課題が明確になれば、必要な設備投資の方向性も自ずと見えてきます。
- 導入機器の候補リストアップ: 解決すべき課題に対して、考えられるソリューション(機器やシステム)を調査します。展示会やメーカーサイト、支援機関から情報収集し、「この工程にはこのような自動化機械が使えそう」といった候補をいくつか挙げておきます。概算費用や導入事例も調べておくと、後の計画策定がスムーズです。
- 現状数値の把握: 投資効果を語るため、現状の作業時間・人員配置・コストなど定量データを計測・記録しておきます。例えば「現在は1日8時間×2名で○○個生産」「月間○○時間をXX作業に費やしている」等のベースラインがないと、効果の説得力が出ません。可能であれば過去数年の推移や今後の需要予測なども用意し、計画の裏付け資料として活用します。
- 支援機関や専門家との連携: 中小企業の補助金申請では、認定支援機関(金融機関や士業、コンサルなど)のサポートを受けることが一般的です。早めに相談役となる専門家を決め、計画書のブラッシュアップや必要書類の確認などを手伝ってもらいましょう。専門家は過去の採択事例や審査ポイントにも精通しているため、客観的なアドバイスが得られます。締切直前になると支援機関も混み合うため、余裕を持って依頼することが重要です。
- スケジュール逆算と進捗管理: 公募要領が発表されたら、締切日から逆算して社内締切(ドラフト完成日、関係者チェック完了日等)を設定します。書類不備があると致命的なので、できれば1週間前には全書類を揃え、電子申請システムへの入力も済ませておくのが理想です。チェックリストを作成し、抜け漏れなく準備を進めましょう。時間が足りない場合は、申請内容の欲張りすぎにも注意です(盛り込みすぎて準備が間に合わなくなるケースもあるため)。
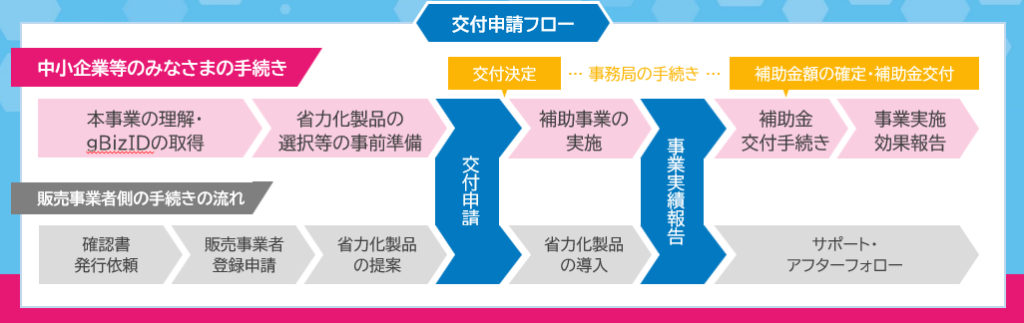
これらを実践することで、「気付いたら締切直前!」という事態を避け、落ち着いて質の高い申請書を仕上げることができます。
特に今回は初回公募の高い採択率を受け、次回以降は申請が殺到して競争激化も予想されます。油断せず、早め早めの準備とスケジュール管理で確実な採択を目指しましょう。
不採択にならないための注意点
最後に、せっかく準備しても不採択となってしまう典型的な要因を知り、対策しておきましょう。第1回公募の傾向や専門家の指摘から、以下のような注意点が挙げられます。
①計画の目的と手段が逆転しない
前述の通り、「この機械が欲しい」が先行する計画は不利です。なぜその設備が必要なのか(課題と効果)を語れない計画書は説得力を欠くため、目的意識を明確にしましょう。
②抽象的すぎる説明に終始しない
「業務効率が向上します」「生産性が上がります」だけでは抽象的すぎます。自社の具体的な業務フローや課題に紐付けて説明しないと審査員には響きません。自社に即した具体例やデータを交えて、計画のリアリティを出すことが大切です。
③賃上げ計画の空洞化に注意
賃上げ目標を掲げるだけ掲げて、その根拠や原資が不明瞭だとマイナス評価につながります。審査側も「本当に賃上げできるのか?」と疑問を持つため、絵に描いた餅とならぬよう具体策を示してください。
④導入後の見通し・リスク評価不足
設備を導入して終わりではなく、導入後にどう運用定着させ効果検証するかまで考えていない計画は不安材料となります。「本当に効果が出るのか」「副作用はないか」という視点でチェックし、必要なら対策を計画に盛り込みましょう。
申請要件の勘違い・漏れ
これは言うまでもなく基本ですが、公募要領の要件を満たしていない申請は門前払いです。補助対象経費の範囲や事業実施期間の条件など、要件の読み違いがないか支援機関ともダブルチェックしましょう。不安な点は事務局への問い合わせも検討してください。
以上の点に注意しつつ準備を進めれば、致命的な失敗は避けられるはずです。特に最初の「機器導入が目的化している」ケースと「汎用的な説明のみで具体性に欠ける」ケースは、不採択の典型例として指摘されています。
裏を返せば、設備導入の目的(解決したい課題)が明確で、具体的な効果と計画が描けていれば採択率は格段に上がるということです。自戒を込めて見直してみましょう。
中小企業が省力化投資補助金で目指せるビジネス変革
本補助金を活用することで、中小企業は単なる作業効率化以上の大きなビジネス変革を実現できる可能性があります。第1回公募の採択企業の事例を紐解くと、省力化投資が企業にもたらすポジティブな変化として次のような展望が見えてきました。
生産能力の飛躍的向上と売上拡大(省力化投資補助金の効果①)
人手に依存していた作業を自動化することで、これまでの人員でも処理量を大幅に増やせるようになります。その結果、受注量を増やしたり新規顧客に対応したりと売上拡大のチャンスが生まれます。
実際に「省力化で生産性を向上し高品質製品の販路拡大へ」といった事例や、「自動化で少量多品種生産に対応し新市場を開拓」といった案件も採択されています。省力化投資は攻めの経営への第一歩となり得るのです。
新商品・新事業への挑戦(省力化投資補助金の効果②)
省力化によって社員の時間的・精神的余裕が生まれることで、これまで手が回らなかった新商品の開発や新事業分野への進出にも取り組みやすくなります。
例えば採択事例の中には「半自動化により省力化・販路拡大・新商品開発の実現」と明記されたものがあり、省力化がイノベーションの呼び水となっていることが伺えます。単純作業を機械に任せ、人間は創造的な仕事にシフトする――中小企業にとって理想的な形を補助金で後押しできるのです。
高付加価値業務への人材シフト(省力化投資補助金の効果③)
単に人件費を削るのではなく、省力化で浮いた人材を戦略分野に再配置することが競争力強化につながります。
ある採択企業では基幹業務システム導入による業務省力化で、従業員を高付加価値事業へ振り向ける計画を掲げています。このように「省力化=人減らし」ではなく「人材の有効活用」と捉えることで、社員のモチベーション向上やスキルアップにもつながり、結果的に企業全体の付加価値向上を実現できます。
働きやすい職場環境の実現(省力化投資補助金の効果④)
重労働や長時間労働が常態化していた職場に省力化投資を行えば、従業員の負担軽減や安全性向上といった効果も期待できます。
実際「重労働部分をロボット化し、老若男女が働ける環境づくり」や「危険作業の自動化で安全性強化」といった目的が掲げられた案件も見られます。働きやすい職場は人材確保にも有利に働くため、省力化=人手不足解消にも直結します。
結果として企業の持続的成長基盤が強化されるでしょう。
地域や市場への波及効果(省力化投資補助金の効果⑤)
中小企業が省力化に成功すれば、取引先や周囲の企業にも好影響を与える可能性があります。
生産性が上がり供給力が高まれば、新たな受注で地域経済に貢献できますし、他社への技術波及やベストプラクティスの共有にもつながります。補助金を活用した成功事例が増えれば、業界全体のデジタル化・省力化の促進にも寄与するでしょう。そうした観点からも、本補助金は単なる一企業の助成に留まらない社会的投資と言えます。
以上のように、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」は単に作業を楽にするためのお金ではなく、中小企業のビジネスモデルを変革し成長軌道に乗せる起爆剤となり得ます。
採択率こそ第1回は高かったものの、今後競争が激化すれば容易には採択されなくなるかもしれません。しかし、本記事で述べた採択傾向や対策を踏まえてしっかり準備すれば、チャンスを掴むことは十分可能です。
ぜひ本補助金への申請を通じて自社の省力化・DXに挑戦し、新たな成長への一歩を踏み出してみてください。皆様の事業の発展と飛躍をお祈りしています。

